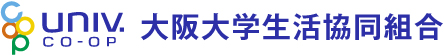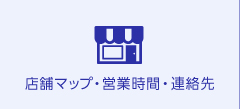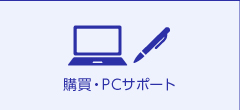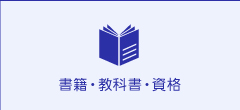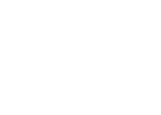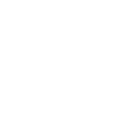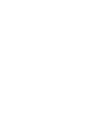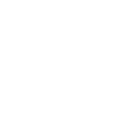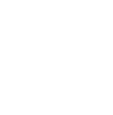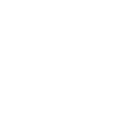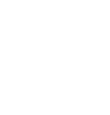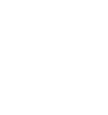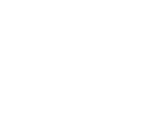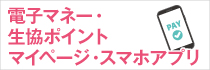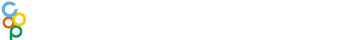今月のおすすめ書籍
 今月のおすすめ書籍
今月のおすすめ書籍

■出版社:新潮社
■発刊日付:2024年7月
■著者:ガブリエル・ガルシア=マルケス 鼓直
■本体価格:1,375円(本体1,250円+税)
■ISBN:9784102052129
蜃気楼の村マコンドを開墾しながら、愛なき世界を生きる孤独な一族、その百年の物語。錬金術に魅了される家長。いとこでもある妻とその子供たち。そしてどこからか到来する文明の印……。目も眩むような不思議な出来事が延々と続くが、予言者が羊皮紙に書き残した謎が解読された時、一族の波乱に満ちた歴史は劇的な最後を迎えるのだった。世界的ベストセラーとなった20世紀文学屈指の傑作。

■出版社:岩波新書
■発刊日付:2024年7月19日
■著者:上脇博之
■本体価格:990円(本体900円+税)(予価)
■ISBN:9784004320210
自民党議員による政治資金パーティー裏金問題は、安倍派をはじめとした派閥が解体された今も、決着を迎えてはいない。政治責任が問われることのないまま、うやむやになってしまうのか。――告発の火付け役である著者が、裏金問題の本質を抉り出し、ウソを見抜く技を提供する。真の政治改革に向けた問題提起の書!

東京スカイツリー カメラ付き携帯 三陸鉄道復旧 明石海峡大橋
■出版社:NHK出版
■発刊日付:2024年7月10日
■著者:NHK「新プロジェクトX」制作班
■本体価格:1,100円(本体1,000円+税)
■ISBN:9784140887233
18年ぶりに復活の群像ドキュメンタリー、待望の書籍化第1弾!
「失われた30年」とも形容されるバブル崩壊の日本。そんな時代にも挑戦者は必ずいる。人に讃えられなくても、光が当たらなくても、ひたむきな仕事がある。情熱と勇気をまっすぐに届ける人気番組が待望の書籍化! 第1弾は4つのテーマに加え、俳優・田口トモロヲ氏の特別エッセイを収載。

■出版社:集英社
■発刊日付:2024年7月
■著者:増山実
■本体価格:1,760円(本体1,600円+税)
■ISBN:9784087718720
「実は、私には、今まで誰にも話してこなかった、秘密があります」
昭和29年に待兼山駅前で、父と母が始めた書店と喫茶店。1階の書店を兄が、2階の喫茶店を弟が継いだが、時代の流れもあり、65年続いた店を閉じることに。
残された数カ月間、月に一度開かれる「夜会」で街にゆかりの人々が語る、とっておきの思いがけない体験、生涯最高の思い出とは……。心あたたまる連作短編集。
(第一話:待兼山ヘンジ/第二話:ロッキー・ラクーン/第三話:銭湯のピアニスト/第四話:ジェイクとあんかけうどん/第五話:恋するマチカネワニ/第六話:風をあつめて/第七話:青い橋)
【著者略歴】
増山 実 (ますやま・みのる)
1958年大阪府生まれ。同志社大学法学部卒業。2012年に「いつの日か来た道」で第19回松本清張賞最終候補となり、それを改題した『勇者たちへの伝言』で2013年にデビュー。同作は2016年に「第4回大阪ほんま本大賞」を受賞した。他の著書に『空の走者たち』『風よ僕らに海の歌を』『波の上のキネマ』『甘夏とオリオン』『ジュリーの世界』(第10回京都本大賞受賞作)『百年の藍』がある。


■出版社: インスクリプト
■発刊日付:1・2巻同時発売 2024年7月
■著者:濱口竜介
■本体価格:1・2巻共 2,750円(本体2,500円+税)
■ISBN:1巻 9784867840061
2巻 9784867840078
『ハッピーアワー』『寝ても覚めても』『ドライブ・マイ・カー』『偶然と想像』、そして『悪は存在しない』へ。カンヌ、ベルリン、ヴェネツィアの世界三大映画祭を制覇し、米国アカデミー賞国際長編映画賞にも輝いた、世界が注目する映画監督・濱口竜介による映画論を、全2冊に集成。1巻目の「映画講座」篇には、仙台・神戸・鎌倉・ソウルなどで開かれたレクチャーをまとめる(すべて初活字化)。映画史上の傑作・名作はいかに撮られてきたのか、その作劇と演出と演技へと迫る映画講座、ここに開講。
私の映画との関わり方、というのは何かと言うと、それはもちろんまず撮る人――この場合は監督として――ということです。そして、もう一つは、もしかしたらそれ以上に映画を見る人、ただの映画好き、一ファンとして、ということですね。映画好きが昂じてそれが職業になるところまで来たので、一応は人並み以上に好きなのだろう、とは思っています。ただ、そんな風に人並み以上に好きであるにもかかわらず、映画というのはどこか、徹頭徹尾私にとって「他・なるもの」であるようだ、というのがほとんど二十年近く映画と関わってきて、私が強く持っている感覚なんです。――本書「映画の、ショットについて」より
「映画をこれまでほとんど見ていない」ような人でも理解できて、しかもその人をできるだけ自分の感じている「映画の面白さ」の深みへと連れて行けるように、という思いで構想した。――本書「まえがき」より
おすすめ新刊紹介「理工書」 [2024年7月1日up]

■出版社:森北出版
■発刊日付:2024年7月2日発刊
■著者:Andrew Gelman (原著), John B. Carlin (原著), Hal S. Stern (原著), & 9 その他
■本体価格:14,850(税込み)(本体13,850円+税)
■ISBN:978-4627097032
ベイズ推測やモデリングの基礎から始めて、ガウス過程、ディリクレ過程、ハミルトニアンモンテカルロといった手法まで、実用的な手法を幅広く網羅。各手法の理論だけでなく、豊富な実例・演習問題をもとに、計算機を用いたシミュレーション、プログラミング手法と応用における注意点までもれなく解説。
大学院生や研究者など、ベイズ統計とその応用に関わる方のリファレンスとしておすすめの一冊。

■出版社:共立出版
■発刊日付:2024年7月3日発刊
■著者:浅芝 秀人 (著)
■本体価格:3,850円(税込)(本体3,500円+税)
■ISBN:978-4320115620
―圏を関係付き箙(クイバー)で表示する方法によって、小さな圏を手作りし、圏のなかで起こっていることを可視化する―
本書では、圏を関係付き箙(クイバー、有向グラフ)で表示し、その集合表現(前余層)とその間の射を図示する手法を用いて、圏論における様々な概念を視覚的に捉える例を作る。本書で目指しているのは、それにより、圏論を理解しやすくすることである。
本書を読むための予備知識としては、集合と写像、集合の上の同値関係と類別の程度を想定している。
圏だけではなく、関手(集合表現)や自然変換をも、箙表現の構造箙を用いて視覚的に取り扱う方法を紹介している点は、本書の大きな特徴である。これによって、特に極限や余極限の理解は劇的に容易になり、豊富な例を作ることができるようになる。本書の後半で解説している随伴関手は、その最初の練習教材として用いることができる。随伴関手については、自然同型を表す竹内外史の著書『層・圏・トポス』で用いられている、多段の式表示をフルに使い、随伴関手の動きを可視化して証明を見やすくしている。また、右随伴を包絡、左随伴を被覆として捉える見方を取り入れている。

■出版社:裳華房
■発刊日付:2024年7月9日発刊
■著者:原 隆 (著)
■本体価格:3,740円(税込)(本3,400体円+税)
■ISBN:978-4785316037
★ がんばる初学者・独学者を全力応援! ★
新進気鋭の若手数学者が贈る、群論の壮大なストーリー。
群の例や例題を豊富に用意し、具体的な群の計算を通じて、抽象的な概念を手を動かしながら吸収できるようにした。本書にはいろいろな“顔”を持つ群が登場するが、それらの群を単に教科書的に羅列するだけでなく、現代数学のどのような場面で活用されるかについても言及した。群の世界はこれほどまでに広く豊饒だったのかと驚かざるを得ないだろう。さらに、関連する話題や数学者の話を「よりみち」や「コラム」で紹介した。
群の“迷宮”へと誘い込む最強の独学本が今ここに──。

■書名:渡辺澄夫ベイズ理論100問 with Python/Stan (機械学習の数理100問シリーズ)
■出版社:共立出版
■発刊日付:2024年7月3日発刊
■著者:鈴木 讓 (著)
■本体価格:4,290円(税込)(本体3,900円+税)
■ISBN:978-4320125155
本書は、渡辺澄夫氏によって提案されたWAICおよびWBICの理論的根拠を与えるとともに、ベイズ統計学のためのソフトウェアStanによる実装を導入し、解析関数、経験過程、代数幾何、状態密度の公式などの数学をできる限りやさしく解説したものである。特に、代数幾何は例を数多く掲載した。対象読者は大学基礎課程の統計学の知識がある方、WAICやWBICの本質を知りたい方、『統計的機械学習の数理100問 with Python』程度の知識がある方を想定している。
「渡辺澄夫ベイズ理論」という言葉は、渡辺氏の30年来の友人である著者が、本書を執筆するにあたって命名したものである。そこには「WAICの正当化」をはるかに超えるドラマがあった。赤池の情報量規準、甘利の情報幾何とならぶ日本統計学の偉業として渡辺澄夫氏の業績を多くの方に知っていただきたいというのが本書の願いである。

■書名:方程式を解く ガロアによるガロア理論
■出版社:現代数学社
■発刊日付:2024年7月21日発刊
■著者:上野 健爾 (著)
■本体価格:3,520円(税込)(本体3,200円+税)
■ISBN:978-4768706398
ガロア方程式論の “第二論文” 邦訳を収録. 未完の論文が主張するガロア理論と群論がめざすものとは? 本書は方程式のガロア理論への入門書であり,それと共にガロアの原論文を読むための入門書でもある.ガロアの論文に書かれている内容だけでなく,生まれようとしている概念をガロアがどのように考え,どのように記述し,定式化しようとして苦労していたかを味わうために,翻訳はできる限りガロアの時代に相応しい言葉を用いることに努めた. 1.3 次• 4 次方程式の古典的な解法からラグランジュに始まる置換群による古典的な解法の群論的な解釈 2.体論を使った3 次・4 次方程式に関するガロア理論 3.ガウスによる円分体の理論の簡単な紹介 4.ガロア理論の現代的な観点,ガロアによるガロア群の定義からガロアの第一論文に記された理論をできるだけガロアの原論文に即し,現代的な体論の観点から記述 5.ガロアが方程式に関して残した主要な著作,いわゆる第一論文,第二論文および,決闘の前夜に記したシュヴァリエ宛の手紙の邦訳を解説.

■出版社:現代数学社
■発刊日付:2024年7月21日発刊
■著者:高田 栄一 (著)
■本体価格:1,980円(税込)(本体1,800円+税)
■ISBN:978-4768706404
大学入試における数学の問題は高校数学の範囲で解けるように作られる.しかしながら,入試における標準程度の問題であっても,教科書だけでの勉強では殆ど太刀打ちできるものではない,というのも厳とした事実である.入試問題が練りに練られて作られるようになり,出題者はどんな解答を期待しているのであろうか? その解答の披露と「将棋力」に対応する「数学解答力」の向上のためにお読みいただければ幸いです. 【内容】 2 次方程式と2 次関数/放物線の問題・今は昔/整式の変形/整式の美/不等式と最大・最小問題/不等式と領域/平面ベクトル/フィボナッチの数列/数列の和と不等式/場合の数と確率/ 他

■出版社:日本評論社
■発刊日付:2024年7月2日発刊
■著者:山田 裕史 (著)
■本体価格:2,860円(税込)(本体2,600円+税)
■ISBN:9784535790186
整数の分割、ヤング図形からシューア函数、そして佐藤理論へ――軽快かつ本格的に組合せ論の魅力を語る、著者ならではの入門書。
【目次】
第0講 まくら
第1講 ロビンソン-シェンステッド対応
第2講 標準盤で遊ぶ
第3講 ヤング束の話
第4講 分割恒等式
第5講 分割単因子
第6講 対称群の表の組合せ論
第7講 対称群の分解行列
第8講 リー環とリー環もどき
第9講 カタランケ
第10講 シューア函数再び
第11講 プリュッカーとグラスマン
第12講 広田微分の周辺

■書名:幾何学と不変量 [増補改訂版]
■出版社:日本評論社
■発刊日付:2024年7月20日発刊
■著者:西山 享 (著)
■本体価格:4,180円(税込)(本体3,800円+税)
■ISBN:978-4535790230
いろいろな幾何学と、それと密接に関連した群とその不変量から導き出される、美しく多彩な世界を描き出す。
群の作用と不変量がどのように幾何学を規定するのか、幾何学で重要な概念の理解に不変量がどう役立つのかを示す。
増補改訂版では、本文全体を見直し参考文献を補った。
とくに第8章以降は大幅な増補を行い、第10章「保形関数とj不変量」を新たにつけ加えた。楕円曲線周辺の話題を群作用と不変量の視点から明快に解説する。

■出版社:サイエンス社
■発刊日付:2024年7月24日発刊
■著者:垣村 尚徳 (著)
■本体価格:2,640円(税込)(本体2,400円+税)
■ISBN:978-4781916095
組合せ最適化は,ルート探索やスケジューリングなど実社会に現れる課題を解決するために有用であるが,そこでは適切な定式化(モデリング)と効率的な計算方法(アルゴリズム)の設計が求められる.本書では,組合せ最適化の理論的な基礎に焦点を当て,特に,組合せ最適化問題の解きやすさ・解きにくさの背後にある理論的な性質を知ることを目指した.
【主要目次】第I部:組合せ最適化の基礎(組合せ最適化/線形最適化の基礎/組合せ最適化モデル)/第II部:効率的に解ける組合せ最適化問題(二部グラフのマッチング/二部グラフの最小コストの完全マッチング/整数多面体と完全単模行列/完全単模行列の組合せ最適化への応用/完全双対整数性と一般のグラフのマッチング/全域木とマトロイド/最小カットと対称劣モジュラ関数/線形代数を利用したアルゴリズム)/第III部:解きにくい組合せ最適化問題に対するアプローチ(近似アルゴリズム/集合被覆問題に対する近似アルゴリズム/固定パラメータアルゴリズム/オンラインマッチング)/付録A:アルゴリズムの基礎/文献ノート

■書名:線型代数20話
■出版社:朝倉書店
■発刊日付:2024年7月2日発刊
■著者:井田 大輔 (著)
■本体価格:3,300円(税込)(本体3,000円+税)
■ISBN:978-4254132021
道具として公式を使うだけでなく,数学自体の面白さを感じて研究に活かすために。
1日1話で学び,抽象的に概念の理解につながる全20話。
【主な目次】
1. 線型代数
2. 行列
3. 行列式
4. 行列式の計算
5. 逆行列
6. ベクトル空間
7. 基底の存在
8. 線型写像
9. 表現行列
10. ベクトル空間の構成
11. ユークリッド・ベクトル空間
12. 固有値問題
13. 正規行列
14. 実対称行列の対角化
15. 最小多項式
16. 一般スペクトル分解
17. ジョルダン標準形
18. 線型微分方程式
19. テンソル
20. 量子力学への応用

■出版社:朝倉書店
■発刊日付:2024年7月9日発刊
■著者:蓑谷 千凰彦 (著)
■本体価格:26,400円(税込)(本体24,000円+税)
■ISBN:978-4254122992
○統計分析で利用される様々な確率分布の特性・数学的意味・展開等を豊富なグラフとともに詳細に解説
○2003年刊行の初版から2回目となる増補改訂を加えた信頼のレファレンス
○増補第3版ではIDB,リンドレー分布,ロジスティック指数分布など6分布を追加

■出版社:岩波書店
■発刊日付:2024年7月12日発刊
■著者:今井 功 (著)
■本体価格:4,730円(税込)(本体4,300円+税)
■ISBN:978-4007314698
古典物理学で扱う様々な方程式は、どのような法則からいかに導きだされるのか。数学を物理に利用するには、このことを理解しておくのが重要である。本書は、力学、電磁気学を学ぶための道具として数学を眺め、その取扱い方を解説する。自然現象の物理モデルから数学モデルを形成し、その構造から物理モデルを統一的に眺め返す。

■書名:解析力学: 基礎の基礎から発展的なトピックまで
■出版社:共立出版
■発刊日付:2024年7月11日発刊
■著者:渡辺 悠樹 (著)
■本体価格:3,630円(税込)(本体3,300円+税))
■ISBN:978-4320036314
解析力学をはじめて学ぶ際にも、発展的な内容を学ぶ際にもおすすめの一冊
解析力学の考え方を用いると、ニュートンの運動方程式だけでなく電磁気学におけるガウスの法則、アンペールの法則などをも統一的な視点から「導出」することができる。その際の指導原理となるのが「対称性」であり、その重要性について強調したことが本書の特色の1つである。
たとえば、光の速さが一定という実験事実と整合するようにガリレイ対称性をローレンツ対称性へと変更することで、ニュートン力学を導くのと同じ要領で特殊相対性理論が自然に導かれることをみる。また、連続対称性がネーター保存量を導き、逆にその保存量が対称性の生成子になるといった関係について学べるようになっている。特に、ハミルトニアンが時間発展の生成子、運動量が空間並進の生成子になることや、電磁場中の荷電粒子のハミルトニアンの具体的な形を理解しておくことは、量子力学を学ぶ際のよい足がかりとなるだろう。
類書にはあまり見られない内容として、スピンの取り扱い、自発的対称性の破れについての議論、ラグランジアンの存在についてのヘルムホルツ条件の導出や、中心力下の運動についてのベルトラン定理の証明なども盛り込んだ。

■出版社:共立出版
■発刊日付:2024年7月11日発刊
■著者:須藤 彰三 (監修), 岡 真 (監修), 吉澤 雅幸 (著)
■本体価格:2,200円(税込)(本体2,000円+税)
■ISBN:978-4320035133
光は古くから人々の興味の対象となっており、紀元前には既に光の直進性や反射・屈折が認識されていました。16世紀に入ると、光の研究は力学とならんで飛躍的発展をとげ、20世紀初頭までに光を波として扱う光学がほぼ完成されました。ヤングの干渉実験は光が波の性質をもつことを示した重要な実験であり、光がマクスウェル方程式に従う電磁波であることも示されました。ところが、光電効果のように波では説明できない現象が発見されたことで、光は波と粒子の両方の性質を併せ持つことが明らかとなり、量子光学が生まれました。レーザーは量子光学の最大の成果ともいえるものであり、私たちの日常生活において不可欠なものとなっています。
本書では、光の波としての性質を幅広くカバーできるように、各章の内容のまとめと30の例題、発展問題を配置しています。マクスウェル方程式に基づく伝播、干渉、回折といった基礎的事項に始まり、レンズ、光線光学などの実際の光学系の設計に役立つ事項を取り上げています。特に、レーザー光が伝播する状態であるガウシアンビームについて詳しく紹介をしています。また、複雑な光学素子の組合せの計算を可能とする、行列を用いた計算方法も紹介しています。これらは、解析的な計算結果を得ることは難しい手法ですが、計算機により数値的な結果を得るための基礎となるものです。さらに、光パルスの時間的特性の取り扱いも示しました。

■出版社:東京図書出版
■発刊日付:2024年7月12日発刊
■著者:八百板 晃 (著)
■本体価格:1,760円(税込)(本体1,600円+税)
■ISBN:978-4866417608
波動は慣性力の伝播
アクティブ消音
・トンネルジェットファンの騒音発生源
・騒音源を見通せる大気空間
光の二面性
・光電効果の光電子放出:円運動電子の軌道ひずみ
万有引力の発生
・原子間の相互電磁誘導

■出版社:朝倉書店
■発刊日付:2024年7月2日発刊
■著者:金井 昭夫 (編集)
■本体価格:6,160円(税込)(本体5,600円+税)
■ISBN:978-4254171860
・RNAは,DNAやタンパク質と並んで生命現象を司る基本的な生体分子である。
・近年,従来知られていた以上に生体内で重要な役割を数多く担っていることが明らかにされつつある。さらに創薬やワクチンなどへの応用も注目を集めている。
・RNAの基本的なはたらきから最近の知見まで,全体像を俯瞰できる一冊。オールカラー。

■出版社:オライリー・ジャパン
■発刊日付:2024年7月25日発刊
■著者:石原 淳也 (著), 倉本 大資 (著), 阿部 和広 (監修)
■本体価格:2,539円(税込)(本体2,300円+税)
■ISBN:978-4814400829
ScratchだけでできるChatGPTによる生成AIプロジェクトを加筆!
小学校高学年くらいの年齢から読める、機械学習入門書の改訂第2版。Scratchの拡張機能を使い、画像認識、音声認識、姿勢検出などのプログラムを実際に作りながら、機械学習のしくみを楽しく学ぶことができます。第2版では新しく「文章生成編」を追加。ChatGPTを使った生成AIプロジェクトにも取り組みます。作りながら学ぶことで、実際の世の中で機械学習がどのように生かされているかを想像し、自分でも機械学習を使った仕組みを考えられる力を養います。

■出版社:工作舎
■発刊日付:2024年6月27日発刊
■著者:原島 博 (著)
■本体価格:3,080円(税込)(本体2,800円+税)
■ISBN:978-4875025641
「俯瞰する知」は冒険への招待状です。—宮下芳明(イグノーベル賞受賞/明治大学教授)
巻2のテーマは人類史! 理科で教わったビッグバンでの宇宙誕生とカンブリア爆発、世界史での人類の食糧生産の始まりと産業革命。宇宙と地球、人類の誕生と発展を、科学・社会の分野の枠を飛び越えつなげていく。

■出版社:ダイヤモンド社
■発刊日付:2024年7月17日発刊
■著者:アンドリュー・ポンチェン (著), 竹内薫 (翻訳)
■本体価格:2,420円(税込)(本体2,200円+税)
■ISBN:978-4478112489
ダークマター、銀河系、そしてブラックホールや量子力学の世界… 。あまりにも広大な宇宙全体を理解するには、理論だけでも限界があるし、LIGOのような最新の重力波望遠鏡を用いた観察も、宇宙のすべてを見通すことなどは、とてもできない。
こうしたアプローチでは「宇宙の様々な現象がどのように相互に作用することで 銀河系や太陽系や、ひいては地球上の生命を生み出すに至ったのか」という大きな問いへのアプローチが欠けている。 そこに現れた救世主が、「スーパーコンピュータ」だ。
本書では、若き天才宇宙学者がビックバンから現在まで「ぶっとんだ宇宙の全体像」を提示する。

■出版社:京都大学学術出版会
■発刊日付:2024年7月17日発刊
■著者:H・ジェイ・メロシュ (著), 山路 敦 (翻訳), & 1 その他
■本体価格:6,930円(税込)(本体6,300円+税)
■ISBN:978-4814005437
惑星表面に存在する多種多様な地形,火山,氷河,土.地球と共通する特徴をもつものもあるが,地球とはまったく異なる姿を見せることもあるこれらを説明する普遍的な原理はなにか.地質現象に着目することによって,千姿万態の惑星や衛星を串刺しにする.地球にとらわれない広い視野で学ぶことで地質現象の奥深さを知る惑星地質学の名著.

■出版社:オライリー・ジャパン
■発刊日付:2024年7月2日発刊
■著者:Piethein Strengholt (著), 村上 列 (翻訳)
■本体価格:4,180円(税込)(本体3,800円+税)
■ISBN:978-4814400713
今日では、データを素早く価値に変換することが求められています。一方、人工知能、クラウド化、マイクロサービスといった新しいソフトウェア提供モデルが、データ管理の方法を根本から変革しようとしています。組織は、分散化が避けられない現実に直面し、責任の分散、データの管理手法、そしてデータの他者への提供方法に関する変革を迫られています。
本書では、将来にわたり堅牢かつスケーラブルなデータ管理を実現するために、組織のニーズを踏まえた次世代データアーキテクチャの設計方法について説明します。また、法規制、プライバシーに関する懸念、データメッシュやデータファブリックなどの新しい技術動向を紹介し、クラウドデータランディングゾーン、ドメイン駆動設計、データプロダクトといった最先端のデータアーキテクチャについて解説します。さらに、データガバナンス、データセキュリティ、マスターデータ管理、セルフサービス型データマーケットプレイス、メタデータの重要性などについても説明します。

■出版社:コロナ社
■発刊日付:2024年7月25日発刊
■著者:浜田 道昭 (監修), 三澤 計治 (著)
■本体価格:5,170円(税込)(本体4,700円+税)
■ISBN:978-4339027358
・ゲノム配列情報解析に必要な,生物学の知識とプログラミングの技術を同時に記載し,プログラミング言語Pythonの解説も加えた。本書で紹介した手法や解析などの一部は,Pythonを用いることで体験することができる。
・実際の解析の現場で参照するため,ゲノム解析で使われるデータファイルのフォーマットを付録にて解説した。